おはようございます。今朝は6時に起床し、朝刊を読み、その後、デスクワークをしています。外は曇り空ですが、雨は降っていません。
昨日は午前がデスクワークでした。机に向かい始めてまもなく、コウノトリの巣のことなどが気になり、1時間ほど出てきました。あちこちにハクチョウがいましたが、コウノトリの姿は見かけませんでした。下の写真は空を飛ぶハクチョウです。飛ぶ姿の撮影は難しいですね。

午前は所有権移転登記の申請書づくりもしました。久々です。これまでの電子データがありましたので、割合と早く終わりました。郵便局へ行った帰り、原之町の旧役場跡地付近にあるイチョウの木が輝いていました。きれいでしたね。

午後からは県立柿崎病院後援会理事会でした。柿崎地区公民館の会議室には後援会関係者、病院長、事務長のほか、県の地域医療政策課の人たちも参加していました。トップのイラストでは、私の正面におられた太田病院長を中心に病院事務長、地域医療政策課などのみなさんを描きました。
会議では楡井会長が挨拶、太田病院長が柿崎病院の現状などを中心に報告し、その後、県福祉保健部の地域医療政策課の担当者が上越地域医療構想について説明しました。そこでは、医療需要の変化、病院経営の現状、地域全体で目指すべき姿などについて言及しました。
医療需要の変化では、「人口減少・高齢化が今後さらに進むことが予想される」「柿崎病院では患者が減少している」「入院患者は予想に反して増えておらず、むしろ減少している」「急性期病院にも回復期患者や介護総統の患者が入院している」ことなどが明らかにされました。
注目したのは地域で目指すべき姿の説明です。ここでは、「人口減少・高齢化の中、これからも医療を残していくために、病床の役割分担と集約が必要」であり、「地域包括ケアシステム」という仕組みの中で関係機関が連携しながら対応していくことが求められているとしました。具体的な姿は明示されていませんが、「人口減少局面でも、引き続き適切に医療を受けることができる」ようにということで、「今よりも手厚い体制で急性期医療・救急医療・周産期医療を受けることができる」「今対応していない高度医療を圏域内で受けることができる」ことなどを強調していました。そして「中期再編」と称して、①中核病院の集約・機能強化、②地ケア病院の集約・機能強化、③医療人材確保に向けた仕組みづくり、④病院間連携に向けた仕組みづくり、⑤地域全体で医業収支改善(経営の持続性確保)を実現していくとしました。さらに「中期再編イメージ」として、上越市では中核病院(高度急性期)を集約&機能強化し、地ケア病院(回復期)の機能・規模適正化にむけた検討ポイントを示し、医療再編後の必要ベッド数は、急性期(中核病院)は418~497床(2023年度は903床)に、回復期は526~571床(2023年度は298床)、慢性期は255~297床(2023年度は307床)だとのべました。全体では、ベッド数を143~309床減らすという見通しを示しました。
私からは、昨年3月に県病院局がまとめた病院経営強化プランで柿崎病院は、令和9年度までに目指すべき方向として、「頸北の入院機能を維持すること、そこでは(回復期・維持期で、軽傷救急患者を受け入れ)、レスパイト入院にも対応するなど6項目書かれている。これを見て安心した。病院をめぐる状況は変化していることはわかるが、この計画は10年、20年の計画ではない。4年間のことを決めたものだ。自分たちで決めたことを基本に据えて検討すべきだ」と訴えました。また、中核病院を1つにするというが公立病院と民間病院(公的病院ではあるが)の統合は難しいと思う。全国的にも例があるのか、と質問しました。
これに対して県福祉保健部などの担当者は、昨年3月に立てた計画を守っていくという明言はせず、病院をめぐる状況が大きく変わっていることをくりかえし説明していました。こんなことでいいのでしょうか。中核病院の統合(具体的には中央病院と上越病院)については極めて難しいことだが、全国的には「兵庫県姫路市で県立病院と民間病院が統合した。また下関市で市民病院と公的病院が統合した事例がある」とのべていました。これは今後の動きを注視していきたいと思います。
後援会理事会が終わってから家に戻り、気になっていた冬の準備をしました。雁木などでの「はめ板」の設置です。これは3年前まで大潟区の弟がやっていてくれたのですが、2年前からは自力でやっています。昨日は30~40分ほどで終わらせることができました。これで一安心です。
きょうは吉川区の敬老会です。その前に直江津の朝市に行きたいのですが、行けるかどうか。
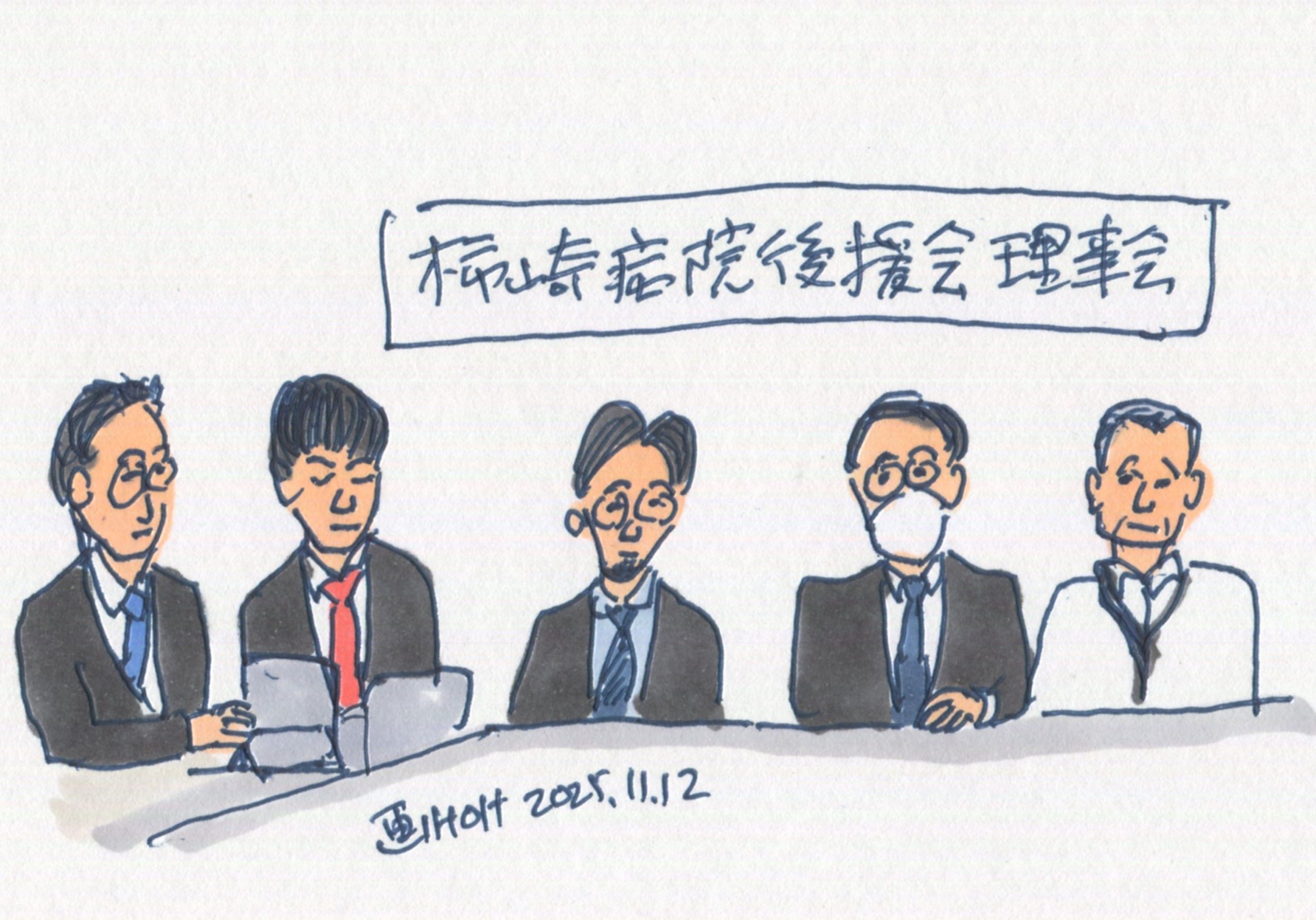


コメント